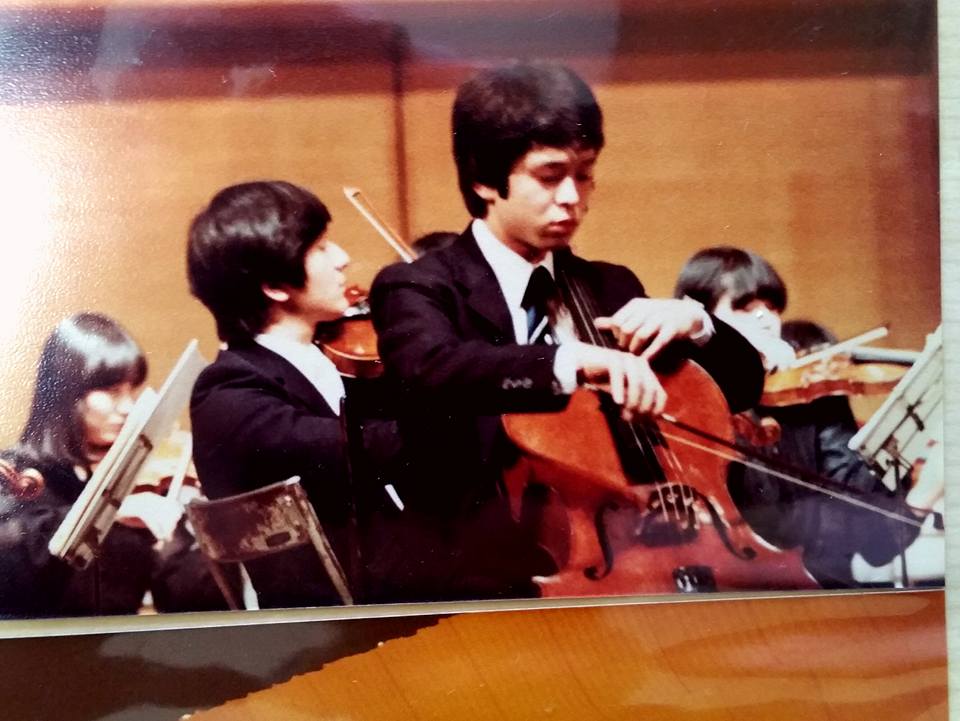今回はヴァイオリンの「弦」と楽器の関係を考えます。
世界中のメーカーががヴァイオリンの「弦」を作って販売しています。多くのプロ、アマチュア、さらにメーカーのプロモーションも含めYouTube動画がヒットします。
それぞれ「この弦は…」「あの減と比べて…」とうんちくを述べたり、実際に演奏して比較していたり。動画で聴く音量や音色は参考になりません。主観的な感想をいくら並べられても自分が弦を選ぶ参考になりません。
そこで今回は、なぜ?弦を変えると音が変わるのか?と言う素朴な疑問に立ち戻ろうと思います。
弦楽器の弦は「音源」です。ヴァイオリンは「擦弦楽器」つまり弓の毛で弦を擦って弦を振動させる楽器です。
弦が振動するためには、弦の両端を「固い物」で固定することと、「引っ張る強さ=張力」が必要になります。小学校や中学校で習った「弦の音の音の高さを変える三つの原理」覚えていますか?
・弦の太さ
・弦の張りの強さ(張力)
・弦の長さ
この中で、弦の長さをヴァイオリンの場合には「駒から上駒(ナット)までの長さ」で、どのメーカーのどの弦も、統一されています。
弦の太さは、細いほど高い音が出るのが原則です。同じ長さ、同じ張力の場合の話です。弦の張力を変えれば、この原則は崩れます。実際に、ヴァイオリンの3番線=D線の方が、4番線=G線より太いことは珍しくありません。見た目は太いのに高い音が出るように「強く張る」必要があるわけです。
張力を強くすれば、高い音が出るのと同時に「大きな音」を出すことがより容易になります。一方で、弦の両端を支えるための力と、駒にかかる力が強くなります。弦を指で押さえる力も多く必要になります。簡単に言えば「楽器と演奏者に負荷が増える」ことになります。
ここでヴァイオリンの弦を「構造」として考えてみます。まずE線=1番線は基本的に金属を細く伸ばし、表面に金属のコーティングをしたものです。他の3本は「芯」の周りに金属の糸を編むように巻き付けて作ります。芯の材料には「金属」「ガット=羊の腸」「ナイロン」が用いられます。金属はほとんど伸縮しません。ガットとナイロンは弾力=伸縮性があります。弾力の強さも様々です。伸びにくい素材を使えば張力が強くなります。
芯の周りに巻く金属の糸の「編み方」「巻き方」によって太さと張力を変えられます。張力を強くすれば弦は当然切れやすくなります。また太くなるため指で押さえることが難しくなります。
次に楽器自体が弦の張力に対して「適当」かどうか?の問題です。ヴァイオリンはペグに巻き付けた側と、テールピースに止める側で張力に耐える力を支えます。その両端と中間にある「上駒」と「駒」の2か所の多寡によって指板部分の張力が変わり、駒にかかる力も変わります。駒を高くすればするほど、聴力が強くなりますが同時に指板と弦の「隙間=弦高」が広くなり、押さえることが困難になります。逆に駒を下げれば押さえやすい反面で、聴力が下がります。
張力の調整はネックと本体の「取付角度」と「駒の高さ」で変わります。高い張力に耐えられる楽器でなければ、表板や魂柱、裏板、ネックにダメージが加わります。音もつぶれた音になります。楽器の「強度」はそれぞれに違います。板の厚さが基準より薄い楽器はm簡単に鳴らせますが強い張力に足ることができません。また、オールド楽器の場合、ガット弦を張ることを前提に作られているので、強い張力の弦で良い音がするとも限り亜m線。楽器ごとの「強度」と響きやすい音域、足りない音域を把握して、適正な弦を選ぶことが重要になります。
弦の種類やメーカを統一する方がバランスが良い場合と、逆に違う種類の弦を張った方が全体のバランスが良い場合があります。低音(G線の音域)が強く出る楽器は「太い」「柔らかい」音である反面、「こもった」「通りの悪い」音にもなりがちです。逆にE線の音域が鳴りやすい楽器の場合、「明るい」「澄んだ」「通りの良い」音に感じる反面「固い」「きつい」「薄っぺらい」音になりがちです。それらを補う演奏方法と、弦を選ぶことで演奏者が弦を気にすることなく、思った音量と音色で4本の弦を演奏できることに繋がります。
弦の種類をバラバラにすると、弦ごとの張力が変わる場合もあります。それも演奏する人にとって負担になります。また、弦の寿命もメーカーや材質によって大きく違います。ガット弦は寿命が長く、テンションの強いナイロン弦の寿命は短くなります。演奏会前に逆算しながら弦を新しいものに張り替えるのが理想ですが、ばらばらに寿命が尽きるのは頭の痛いところです。いくらでも予算がある人なら別ですが(笑)
寿命の尽きた弦は「伸びたラーメン」と似ています。腰がなく、余韻が少なくなります。張ったばかりの弦は「アルデンテ」に似ています。ちょうどよい「弾力=こし」がある状態で、楽器に一番適した弦を選ぶのは大変な時間とお金がかかります。それでも、弦を変えることで楽器の「個性」が変えられるは弦楽器奈良でhなの楽しさでもあります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ヴァイオリニスト・ヴィオリスト 野村謙介