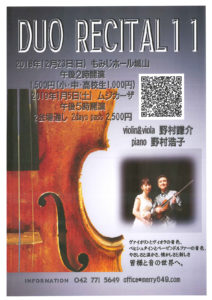2019年6月7日(金)~2019年6月22日(土)
東京医大八王子医療センターに緊急入院しました。
最終的な病名「拡張型心筋症」でした。
緊急入院当初、心不全の状態でした。
生まれて初めて、命に関わる病気にかかりました。
16日間の入院生活で多くのことを学びました。
人の優しい気持ちが、他人の命を救うこと。
生きることへのエネルギーは他人の優しさが源。
病気に気づくことは、自分の無理な生活に気づくこと。
収入のためだけに生活すれば、生きることさえ、できなくなる。
入院生活で知る、高齢者の言動に見るエゴイズム。
患者に接する、看護師や医師のスキルとチームコミュニケーション能力。
今でも心臓は通常の30~50パーセント程度の働きしかしていません。
でも、心不全の状態から完全に脱しました。
さらに言えば、ここ数年来の体調の中で、
最高に良い状態です。
つまり、数年前から私の心臓は日々、弱り身体に警告を出してたんです。
拡張型心筋症は治療法のない難病指定の病気です。
血圧を下げ、尿を出し、心臓の動きを助ける薬を飲み続け、
一日の塩分(6~8ミリグラムまで)、
一日水分摂取量を800~1000ミリリットルに抑えることで
体液の増加を抑え、心臓の負荷を減らしますt。
さらに週に3~5日、有酸素運動をすることで、
血圧維持(心臓のポンプ機能の促進)を心がけます。
「生活に気を付けること」が「生きるための必須」になりました。
今までの自分の「真逆」です。
浩子先生の介護がなければ、入院生活はできませんでした。
「夫婦だから」なんて薄っぺらいことではありません。
人間の他人への優しさが、その他人の命を救うことになります。
それは多くの友人、先輩、後輩、生徒さんからのメッセージや、
お見舞いに来てくださった人との会話からも感じました。
言葉やお見舞いでなくても、レッスンを待っていてくれる生徒さんの
優しさにも、感動して涙が出ました。
ありがとうございました。
病室のほとんどは高齢者、75~90歳の方でした。
人間のエゴイズムは高齢になり、他人の手を借りて生きるようになると
一気に表に出ます。同室にいて、何度となく怒鳴りたくなりました。
耐えましたが(笑)
家族には弱弱しく「助けてオーラ」を出しながら
掃除のスタッフには「今やるなよ!」「あっちにいけよ!」と大きな声で同じくらいのお掃除スタッフを怒鳴ります。。いや怒鳴れます。
担当医が来るとまた「私だけ助けてくださいオーラ」全開。
何人もいました。自分はかわいそうだ。他人にそう思ってほしい。
自分より下だと思う人間には、同情されたくない。関わりなくない。
人間の一番、醜い部部です。
医療センターは若い看護士や研修医が患者に接します。
それを先輩が指導とフォローをし、さら士長や教授が部下を統括します。
入院中の山場、心臓にカテーテル(細い管)を入れる検査の当日、
私の「検査予定時刻」が看護師と医師の間で混乱しました。
医師チームは前日に「明日は午後一番で行います」と私に直接伝えてくれました。
その情報が、看護士たちに伝わりませんでした。
私が新人の看護師に厳しくい言ったのは…
「連絡ミスは仕方ない。あなたたちは午前中の予定で動いている。
先生たちは午後の予定で動いている。どちらかが正しい。
あなたたちの間違った準備が、結果的に命に係わるミスになるかもしれない。
すぐに調べなおせ!」
士長が医師団に確認し、私に誠心誠意謝ってくれました。
医師と看護士のコミュニケーション不足が招いたミスでした。
これは自分の仕事に置き換えて反省しきりです。
数年間より元気に感じる今、
数年間悪くなり続けていた心臓からのメッセージに耳をふさぎ
逃げるように仕事に没頭した「天罰」でした。
出所(退院)し建物から2週間ぶりに娑婆(外の世界)に出て
帰宅し、ぷりんを抱っこし、珈琲を入れて数口、飲んで…
今日からの生き方を考える野村でした。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
メリーミュージック代表 野村謙介